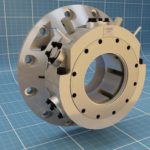今回は「ゼロを目指して組立てる理由」についての記事です。
私は機械装置を組立てをするときに、意識していることがあります。それは、「ゼロを目指して組立てる」です。ゼロとは基準に対して誤差がない状態です。
勿論、精度(測定値)には「ばらつき」や「矛盾」といった「不確かさ」があることは分かっています。つまり、不確かさを理解し、真のゼロは分からないってことを前提としたうえで、ゼロを目指して組立てるべきだと思うのです。
記事の目次
ゼロを目指して組立てる理由
作業意識
皆さんは何かを「組立たり」「調整したり」「加工したり」するときにどのような意識で作業を行っていますか?
-
図面寸法を守る
-
規定値に収める
-
見た目は気にしない
-
取付けできればいい
-
誰かに認められたい
-
精度が良いものを作りたい
-
失敗したらやり直せばいい
例えばこのようないろいろな考えがあると思います。

私の考え
そんな中で、私には長年機械装置に携わってきて一貫している考えがあります。
私の考えはこれです
-
組立て精度は、ゼロを目指して組立てるが基本
「ゼロとは何か?」と言いますと、、、
-
設計の数値(図面寸法) = 基準 = 誤差ゼロ
もし設計値に許容値(数値の幅)がある場合は、、、
-
許容値の中央値 または 任意に固定値を定めて、それをゼロとし組立てる
この考えが私の根本にあります。
なぜゼロを目指すのか
私がゼロを目指す理由はいくつかあります。
-
自分の成長と自己満足
-
客先や第三者から高評価を得たい
-
誤差がある値は基準となり得ない
-
測定器によって得られる値に差がある
-
ゼロを目指しても、それが真にゼロなのか分からない
-
機械装置を動かしたら許容範囲内なのにトラブルが起きる
ざっと書き出すとこのようなことがあります。

これらの理由によって私は、、、
-
ゼロに合わせて組立てることは当たり前
と言う認識です。
それでは、次項から私がゼロを目指す理由について掘り下げて説明しましょう。
なぜゼロを目指すのか
基準や決められた寸法に誤差ゼロで組立てたり、調整することは簡単なことではありません。
構造や部品精度によってはすんなり上手くいく時もあれば、難航することもあるものです。最悪の場合は、構造変更が必要になったり、改造することになったり、部品を再製作したり、、、と言ったこともあるでしょう。
そんな大変な作業が伴うのに、なぜ私がゼロを目指すのか?、、、その理由を説明していきましょう。
自分の成長と自己満足
ゼロを目指すためにこの2つは欠かせません。
-
技術と技能の挑戦
-
こうあるべきと言う目標を達成したい欲求

つまりゼロを目指すことは挑戦であり達成欲を味わうことで、それによって技能の成長や自分自身に自信が付いたりするわけです。はたから見たらそれは「自己満足」なんて思われるかもしれませんが、それがモノづくりの楽しさなのだと思うのです。
そういった日々の積み重ねが、仕事のやりがいになり自分自身のプライドとなるのです。
「精度が良いもの作りたい」、、、そんな思いはモノづくりが好きなら誰しもが持っている気持ちですし、そこに説明は不要ですよね。
客先や第三者から高評価を得たい
精度が良くて悪い印象を受ける人はいないでしょう。
本来は許容範囲内であれば設計上や仕様ではOK、、、なのかもしれません。
でも測定結果が全てゼロできちんと精度が出ていれば、精度にバラつきがあるよりも客先は高評価となるに違いないですし、もっと言えば、測定表も提示できれば客先が受ける好印象は計り知れません。
そういった客先との積み重ねが「信用」となるのだと思うのです。
誤差がある値は基準となり得ない
ゼロで組立や調整ができていないと言うことは、誤差があると言うことです。
例えばユニットAの精度が±0.5mmだとします。その状態で、さらに作業を進めた時に今度はユニットBの精度調整が必要になったとしましょう。そのような場合に、誤差±0.5mmのユニットAはユニットBの基準とはなりません。
±0.5mmのどこを基準とするのか?+0.5mmの部分なのか?マイナス0.5mmなのか?はっきり言ってこんなことを考えていること自体が無駄ですし間違いを起こす元です。
もし、ユニットAとユニットBの距離が100mmとしたときに、ユニットAの+0.5mmを基準として100mmの距離でユニットBを設置したら、、、、本来のゼロからは+0.5mmになってしまいます。でもユニットAからは100mmなのです。
これをどう思うか?、、、と言うことなのです。
測定器によって得られる値に差がある

精度測定は、測定する測定器によって得られる値に違いがあるので、どの測定器で測定してもゼロとなるようにしたいのです。
例えばこのような違いがあります
-
分解能(幾つまで値を示すか?)
-
測定器の種類による精度の違い
-
測定器の違いによる読み取り誤差
測定器によって得られる値に違いがあるからといって、精度が良い測定器や分解能が高い測定器を使用すれば良い、、、、と言うことではありません。
例えば、「ある測定器で測定したら許容範囲の+0.3mmだったのでOKとした」としましょう。しかし、「今度は違う測定器で測定しなおしたら+0.8mmであった」とわかりました。
なぜこのようなことが起きるかと言えば、ゼロを目指していないから、実際は「より外れた値」になることがあるのです。
でも私がこんなことを言うと、「じゃあ初めから高性能の測定器で測定すればいいでしょ」と思う人もいるでしょう。
そこが違うのです。そのような考えの人は精度が高い測定器を過信して、精度が高い測定器を使用してるのにも関わらず結局+0.5mmに落ち着いてしまったりするのです。
つまり使用する測定器は、機械の構造や作業環境やどのような測定器を持っているか?によって限定できないので、その時に使用する測定器で最善の作業を目指さなければ、ゼロに近づくどころか、外れた値になってしまう、、、と言うことなのです。
私はオートレベル(高低差を測定する測定器)を使用することがありますが、一般的に機械装置の組立てには使用されません。この測定器はどちらかと言うと土木関係の測定で使用されることが多い測定器なのです。しかし私は、1/100mmの精度が無縁の土木関係で使用されるオートレベルで、1/100mmの精度出して組立をしています。それは水準器やダイヤルゲージなどで測定することで証明できています。
だから、どのような測定器を使用しようとも、ゼロを目指さずに妥協した値に落ち着いたら、精度は悪くなる一方だとわかってほしいのです。
ゼロを目指しても、それが真にゼロなのか分からない
前述でも触れていますが、測定には測定器の違いによる「分解能」「精度」「器差」や、測定したときの作業者の「読取り誤差」によって得られる値に違いが起きます。
だから、「本当にゼロなのか?」を証明することは簡単ではありません。雰囲気、湿度、温度、使用する測定器、測定方法、、、、、など、何をもって「ゼロ」なのか?は難しいのです。
しかし、現場の組立作業でそれを言い出したらキリがない訳なので、そういった懸念を拭い去るために、その場の測定で得られる値を最善を尽くしてゼロに調整することで「真のゼロから大きく外れていないから大丈夫だろう」と言えるわけです。
*詳しくは下記の記事で説明しています。
参考
機械装置を動かしたら許容範囲内なのにトラブルが起きる
図面や仕様で許容範囲を設けいていることがありますが、その許容範囲内の精度におさまっているのに実際に機械装置を動かしたらトラブルが起きることがあります。

なぜそのようなことが起きるのか
-
許容範囲の値が実際にやった結果に基づいているわけではなく、あくまでも設計値(計算上)の予測だから
-
測定器や測定方法など様々な要因によって、実際には真のゼロから大きく外れている(実際には許容範囲外になっている)
このようなことが考えられます。
私自身の今までの仕事を振り返ると、ゼロを目指して組立ててトラブルが起きたことはそうそうありません。しかし、ゼロを目指さずに許容範囲内で組立をした機械装置にトラブルやチョコ停が起きている場面は幾度となく目撃してきました。
はっきり言って、機械装置に火を入れて上手くいくかどうか?なんて予測不能なのです。どうなるか分からないのです。だからこそ、機械装置の精度が少しでも高くなるようにゼロに拘るべきなのです。
ゼロを目指して組立てる理由まとめ
私がゼロを目指す理由を考えてみますと、それぞれに私なりの理由があります。
これぐらい強い気持ちがないと、異変に気が付く感性、設計へのフィードバック能力、原因追及の思考、なども育たないと思います。
何かの異変が起きても「あれー?なんでだろう・・・?まいっか」なんて感じで何かを見逃してしまうことがないようにしたいものです。
参考
感性には2つの意味があります。
「事実を正しく認識できること」と「目に観えていないことを感じること」です。
「許容範囲だからいいや」と思ったら成長停止
妥協根性だと成長しない
さて、ここまでは私のゼロを目指す理由について説明してきました、、、少し視点を変えてお話ししましょう。

もし機械装置の組立をしていて「許容範囲だからいいや」と思ったら、、、、、もうその人は「成長停止」だと思います。
ゼロを目指してやった結果、±0.02mmとか、±2mmとか、になることはあるかもしれません。しかしそれは、ゼロを目指して試行錯誤した結果であって、作業をする前から「±0.02mmでOK」の考えで作業をしたのとでは「圧倒的な違い」があります。
具体的にどのような違いがあると言うと、、、
-
「ゼロを目指して試行錯誤」 = 「志が高い」
-
「許容範囲だからいいや」 = 「妥協根性」
作業を終えたときの結果が同じだとしても、「気持ち」に大きく違いがあります。
志が高い人と妥協根性の人の成長を比べたとして、余程のことがない限り志が高い人のほうが、技能、知識、経験、信頼、信用、あらゆる面で優っていることでしょう。
そんなことを言うと「そんなの関係ないでしょ」「そうとは言い切れない」と思う人がいるかもしれません。
では話を変えて、、、
ある大会に出場したAさんとBさんがいたとしましょう。お互いに同じ結果で表彰台には上がれませんでした。
-
Aさん「今日はこんなもんかな、すこし体調も悪かったし(妥協根性)」
-
Bさん「なぜ結果がでないんだ、動画でフォームの確認をしよう。今後の練習メニューはコーチと相談して見直そう(志が高い)」
さて、今後より良い結果が望めるのはどちらでしょうか?
これと同じことが「ゼロを目指す人」と「許容範囲だからいいやの人」の違いなのです。
妥協して起きること
組立精度が低いと、数値的には許容範囲であってもこんなことが起きます。
なにが起きるのか、、、
-
客先は満足しないかもしれない
-
作業者の技量は成長していない
-
普段の作業で妥協しているとゼロに合わせる作業ができなくなる
-
本当に問題なく稼働できる保証がない。動かしたらトラブルが起きる
このようなことが言えると思います。やっぱり妥協して良いことはありませんね。
もし、「良いこと」があるとすれば、それは「ゼロを追求しない分、作業時間が短くて済む」ぐらいでしょう。
どうすればゼロを目指す組立てができるのか
作業者の気持ち次第です
どうすればゼロを目指す組立ができるのか、、、
全ては作業者次第です。誰が何を言っても結果、、、、、作業者がどうするか?です。
だからこう思ってください。「絶対にこの数値に合わせるんだ」と。
私はいつもこの言葉を自分に言い聞かせています。

でもきっとこんなことを言われるでしょう
「こだわりすぎでしょ、いつまでやってんの」
でも、全く気にする必要はありません。こだわるのは今自分ができる最高のクオリティで機械装置を完成させることが使命だから仕方がありません。
だから時間もかかるかもしれませんが、そもそも時間がかかるような構造が悪いでしょう。そこにも気が付けば、次回の設計に改善すればいいだけです。
自分から逃げてはいけません。自分に負けてはいけません。絶対にできます。
やるか?やらないのか?ただそれだけです。
私は外さない
私の場合は「ゼロを外す」ことは殆どありません。それはゼロにするための手段を選ばないからです。
調整できなければ、調整できる構造に変えてしまえばいいわけです。無茶苦茶だと思われるかもしれませんが、これは私の本気の考えです。

試行錯誤するから人間は成長し、自分の引出し増えていくのです。
だからゼロじゃなくても設計上はOKかもしれませんが、組立工としては感心できません。機械装置も客先も自分自身も、、、、全てがハッピーでなければベストな仕事ではないでしょう。
ゼロを目指して組立てる理由のポイントのまとめ
それでは、ゼロを目指して組立てる理由について重要なポイントをまとめておきます。
ポイント
- 組立て精度は、ゼロを目指して組立てるが基本
- 許容範囲の精度(誤差)は設計や仕様では間違っていなくても、うまくいかないことが多い
- 妥協する人は成長停止
以上3つのポイントです。
「許容範囲だからいいや」と言う人がいたら聞いてみたい、、、、「それであなたは本当に満足ですか?」と、、、
参考
*機械の精度の考え方を学ぶのにおすすめの本です
関連記事:【精度測定/精度調整】
以上です。