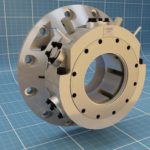今回は「メーカー側とユーザー側のMP情報の活用方法」についての記事です。
安定した製品を供給するために機械の自動化は欠かせませんが、その反面、生産現場では日々不具合が発生しています。そのため、不具合を収集したMP情報をもとに改善をおこなうことが不可欠となります。
一般的にMP活動をおこなうのは設備メーカー側ではなく、実際に設備を使用して製品を生産しているユーザー側です。ところが、不具合を低減するためには設備メーカーも積極的に取り組んでいかなければ問題解決しません。
このような背景のもと、今回の記事では、設備メーカー側とユーザー側のMP情報の活用について、私の考えをまとめておこうと思います。
メーカー側とユーザー側のMP情報の活用方法
MPと設備の関係
MPとは生産現場でよく耳にする言葉で、保全予防(MP:Maintenance Prevention)と言う意味ですが、聞きなれない人にとっては「一体なんのこと?」って感じだと思います。
MPの活動と目的はコレです
-
新規設備や既存設備の不具合を改善すること
- 設備の不具合を改善することで、生産能力と品質を向上させる
*設備とは機械や装置やシステムなど生産に欠かせない機器のことです

「不具合」と言いますと、一体どのようなことが不具合になるのか?漠然としていますよね。
私は、不具合をこのように解釈しています。
- 設備を稼働させることができない状況 = 停滞 = 不具合
- 設備が関係する作業に後戻りが発生する = 不良品 = 不具合
- 「労災事故」と「クラッシュ」が発生するリスクがある = 不安全 = 不具合
*不具合と聞くとネガティブに感じるかもしれませんが、いいモノをつくるために必要なことなので、悪いことではなく前に進むために必要なこと=ポジティブに受け取りましょう。
設備を稼働させることができない状況には、「部品交換や段替えに時間がかかる」「ソフトにバグがある」「スイッチやタッチパネルのレイアウトが悪くて操作がしにくい」「チョコ停する」など、時間的なロスがあります。設備が関係する作業に後戻りが発生する状況には、「機械精度の劣化」「機械の破損」「ポジションのズレ」など、動いてはいるけど正しい状態ではないので不良品を生産している状態です。このような現象は、生産能力と生産するモノの品質が低下します。設備の安全性は一番に優先すべきことです。「作業者が巻き込まれる」「可動部がクラッシュする」といった状況は、設備を稼働させる以前の問題なので、絶対に改善しなければなりません。
私は機械メーカー側の人間なので、MPを初めて耳にしたときは「ピンとこない」感じでしたが、ユーザーの生産工場でおこなわれているMP情報の収集と改善を目の当たりにして、機械メーカーとしても一緒になって取り組むべきだと感じました。
そのため、ユーザーの生産現場でおこなわれているMPを、機械メーカー側にも取り入れる活動をしています。内容は、「設備を設計、製作、組立、試運転、の過程で発生する不具合」を社内で改善する取り組みです。
これによって、「設備の品質が向上」「後戻りが少なくなる」「ユーザーに指摘されることが少なくなる」「独自のノウハウが身につく」など、、、成長できるキッカケを得ることができます。
参考
MP情報の収集
MP情報とは、現場で起きた不具合を収集したもののことで、不具合がない設備をつくるため欠かせない情報です。
MPの収集は、設備メーカー側で発生した不具合と納入後のユーザー側で発生した不具合を、ごちゃ混ぜにせずに切り離してMP情報とします。
メーカー側とユーザー側のMPは分けて考える
-
設備メーカー側のMP・・・設計、製作、組立、試運転、据付、立上げ、の過程で発生する不具合
-
ユーザー側のMP・・・日々の生産稼働の中で発生した不具合
設備メーカー側のMP情報は、社内の関係部署に共有して、改善案を設備にフィードバックします。もし、大幅な設計変更が必要な場合は、ユーザーの仕様に関係してくるので、変更内容をユーザーと共有して承認後に改善するとよいです。
ユーザー側のMP情報は、メーカー側の問題とユーザー側の問題に分けられます。メーカー側のMP情報は、メーカーと共有して、既存設備は「無償対応で改善」または、「追加費用必要なら優先順位を決めて改善」することになります。新規設備の場合は、設計段階でMP情報を盛り込むことになりますが、改善した結果がさらなる不具合を生むことがあるので、図面検討の段階でメーカーとユーザーが協力して検討します。

MPの収集のフローはこうなります
-
不具合が発生
-
手書きで記録 OR PCに入力
-
MPを抽象化したキーワードに分類、集計する
-
関係各所とMP情報を共有して、改善する項目を決める
-
新規設備、既存設備にフィードバック(改善)する
不具合が発生したら、どのような内容であっても記録するようにします。結構ありがちなのが、「これは記録しなくていいや」「これぐらいはよくあること」のように個人の意見で記録をする、しない、の選別をしてしまうことです。なにを改善するのか?は集計したとき、フィードバックしたときに判断するので、改善のネタを捨てることがないように、どのような些細なことでも記録するように心がけてください。
記録して集めたMPはデータ化して見える化します。ポイントは、5W1Hをお手本に細かく分類して、分類した項目を集計することです。どこの部分で発生したのか?発生した状況は?どのように対処したのか?どこの部署に関係することなのか?、、、などなど客観的に判断できるようにします。
参考
*不具合の集計についてはこちらの記事をご覧ください
-

-
設計や部品製作などの問題を抽出する【問題のデータ化】
記事の目次1 設計や部品製作などの問題を抽出する1.1 繰り返される問題1.2 問題解決の糸口1.3 客観的に判断する ...
続きを見る
MP情報を共有して改善する
MP情報の改善は、設備メーカー側とユーザー側で対応が少々違います。
設備メーカー側が収集したMP情報の改善
-
早急に対応が必要な場合は随時共有し設備に反映する
-
今後、改善していく項目は一案件終わったら集計して関係部署と共有し意見交換する
ユーザー側が収集したMP情報の改善
-
生産に与える影響が大きい不具合は、早急にメーカーに対応させる
- ユーザー自身で対応できる項目は、生産技術や保全で改善する
-
設備メーカー範疇のMP情報は時期を見てメーカーに設備改造で対応させて、将来の設備に展開する
改善の優先度が高い場合は、不具合発生から改善までのスピード感が必要なので、その場の状況に応じて臨機応変に対応できる環境づくりが必要です。
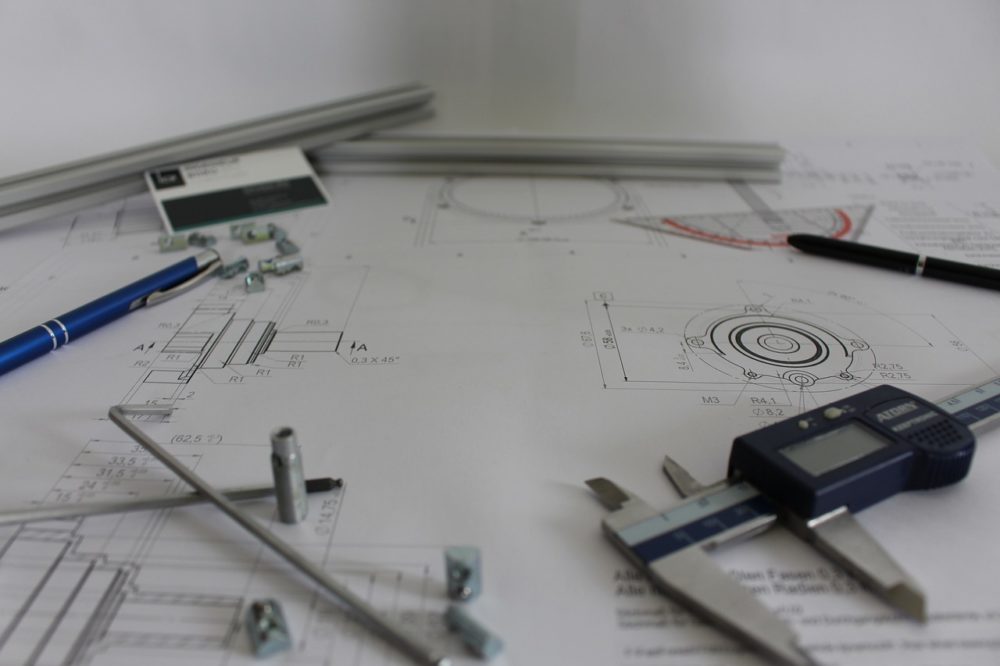
設備を製作している過程の不具合や、納入後に発生する重大な不具合は、費用のことは考えずに早急に改善するようにします。一度受注してしまえば、ユーザーに検収してもらわなければ費用を回収できませんし、不具合を放置すれば信用にかかわります。なので、納期を守ること、仕様を守ること、不具合がないこと、を最優先して、対応することがメーカーには必要です。もし、費用が圧迫しているようなら、ユーザー側に追加費用の交渉をするのもアリですし、今後、同じ不具合を繰り返さないためにMP情報を社内で活用していきます。
設備メーカー側のMP情報は会社の財産であり、品質の高い設備をユーザーに提供する上でとても大切な情報です。ところが、実際に社内でMP情報を運用してみると、なかなか改善しないことが多いです。その理由は、「部署間の不仲」と「プライドによる反発」が一番の要因です。MP情報は「実際に現場で発生した不具合=事実」なので、反発したり、言い訳したり、人のせいにするのは全くの見当違いなのですが、感情的になってしまうことが多いのです。なので、MP情報は「批判」と受け止めずに「最高のものづくり」をするために必要な情報、ってこと全員が認識しておく必要があります。
ユーザー側は、生産が始まってから不具合が発生しないように、メーカーの設計段階からしっかり精査します。改善が必要なMP情報は、設備の見積りのときか、発注の段階でメーカーに改善要求します。設備の仕様書に盛り込んでおくのもOKです。その後、設備が完成する間にこまめに「立ち合い」をします。実際の設備の状態を見ると、納入前に改善しなければいけないことが結構みつかるものです。この時、大抵問題になるのが「納期」と「費用」です。設計が終わっている段階で改善が発生すれば、後戻りの作業になるので当然時間がかかりますし、費用もかかります。そもそもは、設計段階で図面検討が出来ていれば、被害は最小限になるのですが、関係者の協力を得ることができなかったりすることもあるので、MP情報の改善と図面検討が確実にできる「仕組みづくり」にも取り組む必要があります。
ポイントのまとめ
それでは、メーカー側とユーザー側のMP情報の活用方法について重要なポイントをまとめておきます。
ポイント
- MPの目的は設備の不具合を改善して生産能力と品質を向上させること
- 不具合とは「設備を稼働させることができない状況」「設備が関係する作業に後戻りが発生する」ことです
- 不具合が発生したらどのような内容であっても記録しMP情報とする
- MP情報が確実に改善できるような仕組みづくりが欠かせない
以上4つのポイントです。
*MP情報については、TPMの本で学ぶことができます。
関連記事:【仕事と思考】
以上です。