今回は「「見える化」を組立業務に取り入れる」についての記事です。
見える化とという言葉、、、聞いたことがある人は多いと思います。特に製造現場では積極的に取り入れられている印象ですね。見える化を業務により入れることで、作業効率が向上し問題の早期発見にも貢献する取り組みです。
実は私は数年前から機械装置の組立業務に見える化を取り入れているのですが、難易度が低く簡単に効果が得られる見える化もあれば、難易度が高く効果が得られにくい見える化もあり悪戦苦闘しています。
今回の記事では、私が実際におこなっている見える化と実際にやってみてどうだったのか?について紹介しようと思います。
記事の目次
「見える化」を組立業務に取り入れる
見える化とは、目で見て判断/管理できる環境づくりのことです。
私はこの見える化を下記のように解釈しています。
-
見えているものをより見えやすくする
-
目に見えないものは具体化して目に見えるようにする
これにより、直感的に物事が判断できるようになります。

見える化によって得られる効果はコレです
-
管理がしやすくなる
-
異常や問題に早く気が付く
-
情報の共有が早く、共通認識を得られやすい
簡単にまとめるとこのような効果があります。
私はこのような効果を得るために、見える化を自分の環境にも取り入れたいと思い機械装置の組立に応用できることを考えてみることにしました。
機械組立の環境に応用できること
見える化を機械装置の組立て業務に落とし込んで考えてみました。
組立における見える化
-
技術 の見える化
-
知識/思考 の見える化
-
道工具や材料 の見える化
-
案件別の進捗、予定、問題、組付け精度 の見える化
-
問題点 の見える化
この5点が組立作業における見える化だと思いました。

この5つの見える化を実施することで下記の効果を期待できます。
-
作業スキルのムラ(個人差)を無くす
-
無駄な思考を無くし、重要な作業に時間を費やせるようにする
-
道工具など必要な物資の管理をしやすくする
-
誰が見ても何の作業をしているか?今どうゆう状況なのか?が分かるようにして、問題の早期発見と信頼性の向上
-
問題や不具合を繰り返さない。技術の進歩
このような効果を得られれば、機械装置の組立業務は大きな成長となると思い見える化を実行することにしました。
目で見て判断と管理ができる環境づくり
前述で考えた、組立業務の見える化は下記の5つでした。
-
技術 の見える化
-
知識/思考 の見える化
-
道工具や材料 の見える化
-
案件別の進捗、予定、問題、組付け精度 の見える化
-
問題点 の見える化
この5つについて実際に実行したので、次項から紹介していきます。
技術の見える化
技術の見える化は、作業方法を資料化(見える化)して作業者に教育とルール化の徹底をしました。さらにその中から重要な事柄をピックアップして作業エリアのホワイトボードに明記(見える化)していつだれでも直ぐに確認できるようにしました。

具体的には下記の4点です。
-
精度測定に使用す測定器を場面ごとに決めておく
-
どれくらいの精度なら合格か?の判断を過去の事例から判断できるようにする
-
良くあるパターンの精度調整方法を教育
-
過去に問題が発生した事案の対策方法の共有
この見える化によって得られる効果は、、、
-
作業スキルのムラ(個人差)を無くす
このようなことが期待できます。
知識/思考の見える化
知識/思考の見える化は、頭の中にある知識/思考を資料化して見える化することで作業者に教育しました。
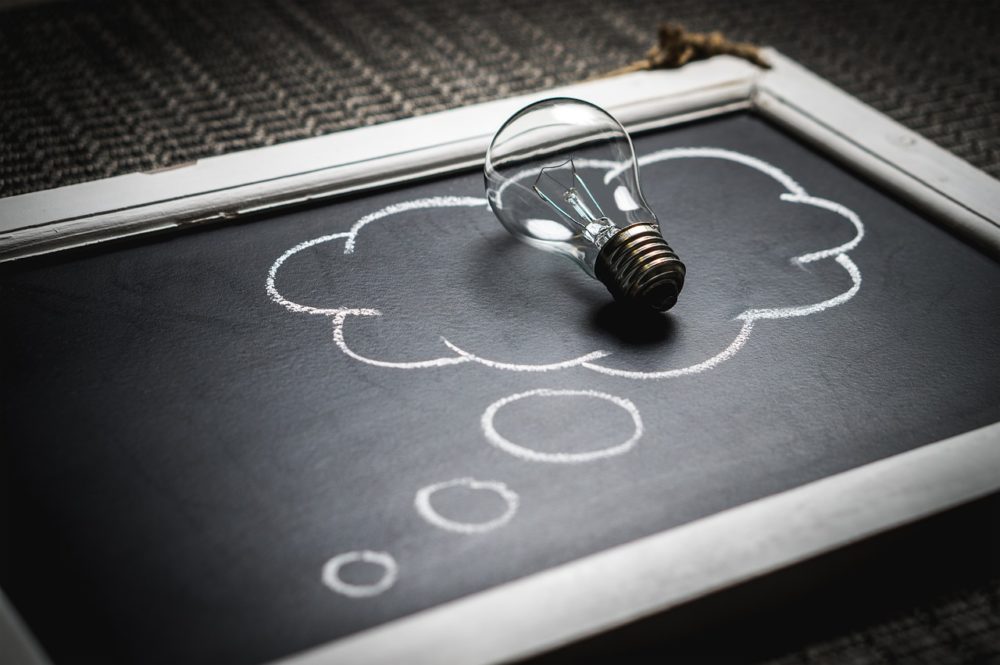
具体的には下記の3点を資料化しました。
-
購入品の組付け時に注意すべきこと
-
材料や加工方法に精度の違い
-
問題が起きた時の原因追及方法
この見える化によって得られる効果は、、、
-
作業スキルのムラ(個人差)を無くす
-
無駄な思考を無くし、重要な作業に時間を費やせるようにする
このようなことが期待できます。
道工具や材料の見える化
道工具や材料の見える化は、機械装置の組立の作業環境の改善です

具体的には下記の5点です。
-
道工具を種類別に棚に整理、テプラで番地を決めて置く
-
離れた場所でも認識できるように看板(名板)を付ける
-
必要な在庫数が分かるように棚を区切る
-
材料を注文する時の為に、型番や数量などを棚に明記しておく
-
組立て部品は棚に整理し、図面も棚に収納し必要なものを1っカ所にまとめて置く
この見える化によって得られる効果は、、、
-
無駄な思考を無くし、重要な作業に時間を費やせるようにする
-
道工具など必要な物資の管理をしやすくする
このようなことが期待できます。
案件別の進捗、予定、問題、組付け精度の見える化
案件別の進捗、予定、問題、組付け精度の見える化は、作業している内容が第三者でも分かるようにホワイトボードに記載、表示して見える化しました。

具体的には下記の3点です。
-
案件別にホワイトボードを設置し、進捗、予定、精度などを記載する
-
作業時間をシートに記録しホワイトボードに貼り付ける
-
問題や不具合をシートに記録しホワイトボードに貼り付ける
この見える化によって得られる効果は、、、
-
誰が見ても何の作業をしているか?今どうゆう状況なのか?が分かるようにして、問題の早期発見と信頼性の向上する
このようなことが期待できます。
問題点の見えるか
問題点の見える化は、どんな問題がどのくらい起きているか?を資料化して共有しました。

具体的には下記の2点です。
-
案件ごとに問題や不具合を記録/集計しデータ化。年間の発生件数が分かるようにする
-
各部署に集計データを共有する
この見える化によって得られる効果は、、、
-
問題や不具合を繰り返さない。技術の進歩
このようなことが期待できます。
組立業務の見える化をやってみた結果
さて、ここまでで紹介した組立の見える化、、、、実際にやってみてどうだったのでしょうか、、、、?
実際にやってみると難易度が低い見える化と難易度が高い見える化があることに気が付きました。
難易度が低い見える化
-
道工具や材料 の見える化
-
案件別の進捗、予定、問題、組付け精度 の見える化
これらは直ぐに実行できて効果も表れやすいです。
難易度が高い見える化
-
技術 の見える化
-
知識/思考 の見える化
-
問題点 の見える化
これらは、技術と知識を資料化する難しさと、問題点のデータを他部署と共有しても温度差があると言う壁があり簡単には見える化して効果を得ることは難しいと感じました。
しかし、難易度が高いとは言え見える化するメリットはあるわけで、簡単にあきらめることはできません。今後も引き続き取り組んで、やり方を変えるなどしながら見える化を進めようと思っています。

さて今回の組立業務の見える化を総合的に検証してみますと、全てがうまくできたわけではありませんが相当な効果を実感しています。
見える化による実際の効果
-
短納期対応
-
無駄な残業の低減
-
組立精度向上
-
作業環境向上
どうでしょうか。見える化をやる前とやってみた後では相当な成長が得られたと思います。
今後も継続して見える化を推進していくべきですね。
まとめ
今回は、「見える化」を組立業務に取り入れるについて、私が実際にやってみた方法ややってみてどうだったのか?について紹介してみました。見える化はどのような業種にも応用でき、複数の部署が関わったり、チームで仕事をする場合、第三者にアピールする場合など様々な状況に応用でき、その効果も期待できると思います。参考にしてください。
*見える化の参考にはこちら
関連記事:【仕事と思考】
以上です。
